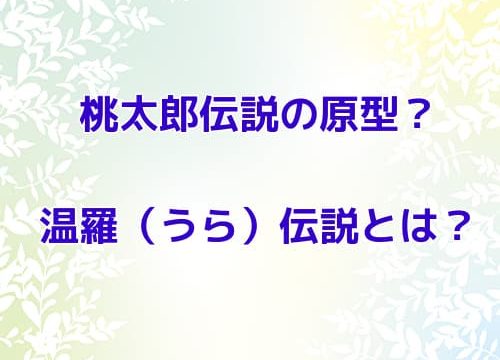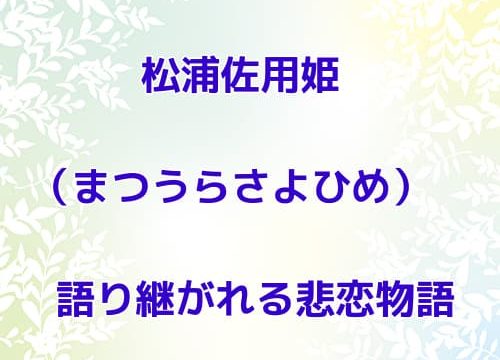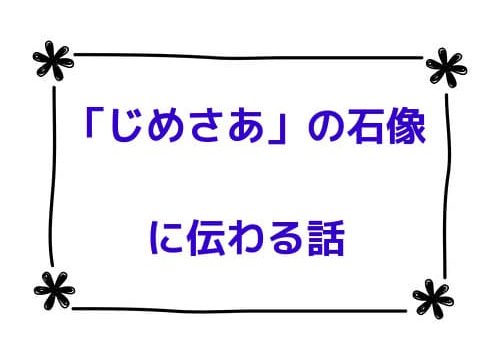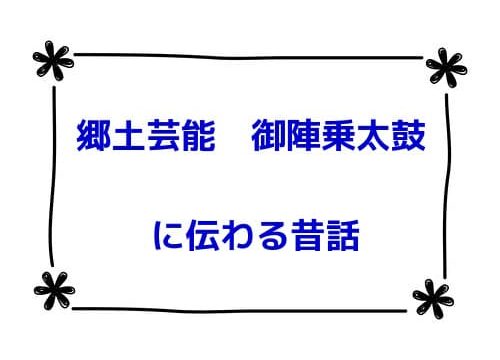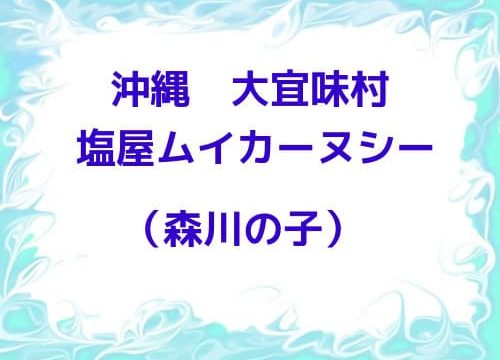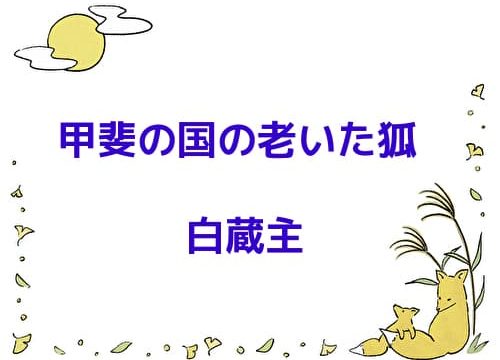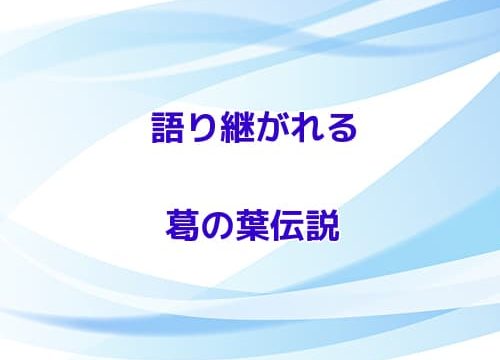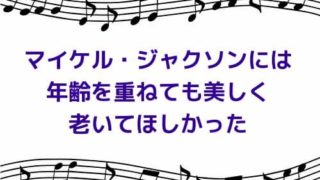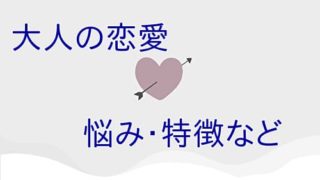江戸時代は仕事の種類も多く、今の時代とは違って手仕事に頼っていた時代でした。
自分で商売を作って物を売るとか、壊れた物を修理する仕事もありました。
当時の商売人は知恵を絞り、小さな仕事かもしれませんが、強い信念を持って商いを行っていた人々もいました。
江戸時代の「虫売り」という商売は、この時代の日本ではかなり儲かる商売であったようです。売られていた昆虫は、蚕、蛾、コオロギ、バッタ、カブトムシ、ハチなどが主で、主に夏の間に採集されました。
虫売りというビジネスが流行ったのです。高値で取引され、需要も多かったそうです。
江戸の人々は商いが上手であったので、今の時代でも参考にできることが多いようです。
江戸時代「虫売り」というビジネスが流行った
江戸時代(1603-1868)には、昆虫ビジネスはかなり盛んで、この国の経済インフラとして欠かせない存在でした。
江戸時代の昆虫商には、商品を持って移動して個人客に販売するもの、特定の地域や市場で独占的に営業するものなど、さまざまなタイプがありました。
特にカブトムシやハチなどの昆虫は、薬効があり、食べると健康や知性が向上すると信じられていたため、日本では人気があったのです。
昆虫は、昆虫採集業者から入手し、小売店や個人客に販売されました。
また、江戸時代には昆虫を商売にする人が多く、趣味で自然観察日記を書き、出会った昆虫の情報を文章にすることもありました。
江戸時代後期の「守貞漫稿」(もりさだまんこう)に書かれていた「虫売り」では屋台を路傍に据えて虫を売っていたそうです。
守貞漫稿(もりさだまんこう)というのは、
守貞謾稿(もりさだまんこう、守貞漫稿とも)は、江戸時代後期の三都(江戸・京都・大阪)の風俗、事物を説明した一種の類書(百科事典)である。
著者は喜田川守貞(本名・北川庄兵衛)。起稿は1837年(天保8年)で、約30年間書き続けて全35巻(「前集」30巻、「後集」5巻)をなした。
刊行はされず稿本のまま残されたが、明治になってから翻刻された。1600点にも及ぶ付図と詳細な解説によって、近世風俗史の基本文献とみなされている。Wikipedia
売る虫も「蛍」が一番、その他は鳴き声の美しいものでした。
こおろぎ、松虫、鈴虫、くつわ虫、ヒグラシなどです。
江戸では虫かごも丁寧に作られ、扇型や船型などが用いられたそうです。
 虫売りWikipediaより
虫売りWikipediaより
虫売りの商売は天保の改革(1841年頃)水野忠邦によって突然禁止されました。
なぜ禁止されたかというと、虫売りの姿が粋でしゃれていたそうで、チャキチャキの江戸っ子でありました。
昔、時代劇で観たことがありますが、手ぬぐいを頭に巻いて粋に歩き、その後ろを虫籠をかついだ下男がついて行くというものです。
それが年々華やかになり競い合うようになったので、禁止されたとのこと。
小泉八雲は江戸時代の虫売りに興味を持ち、詳しく紹介しています。
江戸で最初に虫売りを始めたのは、神田の煮売屋忠蔵(にうりちゅうぞう)という人で、屋台で物を売り歩いていたときに鈴虫の音色の美しさに気づき、たくさん捕まえて帰り自宅に囲いを作って楽しんでいました。すると近所の人たちが鈴虫を欲しがったのです。
欲しがる人が余りにも多いので、商売替えをして虫売りを始めたとのこと。
そして虫の飼育も始めてしまいました。
カンタン・クツワムシ・松虫などを飼育して町中を売り歩きました。
そうすると真似をして虫を売り始める人が出てきます。
虫売りは増えすぎて、江戸市中の虫売りは三十六人までという法令まで出されたのです。
明治時代の虫売り
初夏から初秋へかけての縁日の夜に虫売りが鈴虫、松虫、キリギリス、クツワムシ、こおろぎなどを売っていました。
5月28日不動の縁日から虫売りは登場して、虫を養殖していた卸問屋もあったということです。
蛍専門の虫売りもいたというので、蛍はこの時代も人気があったのだと思います。
あせちりんの灯がようやくまばらになったはずれの方で、親爺が紗張りの容器に草の葉を入れ、時々はじょうろの水をかけていた。
暗闇のなかに青白いほのかな光りが数知れず明滅しているのを、手に手にうちわをもつ浴衣がけの人達が囲んで見ていた。
虫売りの親爺は、子供にねだられて買う客のために、青い蚊帳地を張った、円盤形の曲げ物の中に、微光を点滅する蛍を一つずつ、ゆっくりと入れるのだった。
<参考文献・大江戸商売ばなし・興津要 お江戸の意外な商売事情・中江克己>
いろいろな虫
5月の終わり頃から虫が増えてきて、殺虫剤を買って退治したり大変だったりしますね。
癒される小鳥たちのさえずりも虫の存在によって成り立っているとは思うのですが、さすがに害虫は嫌ですよね。
先日も大きなスズメバチを見つけて大騒ぎをしました。
6月に入ると蛍の季節で、全国で観賞会が開かれたりします。
今の時代も蛍は多くの人に愛されていて、幻想的に舞う姿を楽しみにしている人たちも多いです。
夏になると江戸時代や明治時代に売られた美しい音色の虫たちの声も、聴くことができますね。
♪虫たちの音色を楽しんでみてください。
自然のシンフォニーには不思議な落ち着きがあり、変化する季節の美しさを再認識することができるのです。
虫たちだけでなく、早朝の散歩では、太陽が昇るにつれて、さまざまな種類の鳥が挨拶の合唱をするようになり、自然の魅力の新たな一面を発見することができます。すべての生き物が共存し、互いに助け合い、命の循環が成り立っているのです。