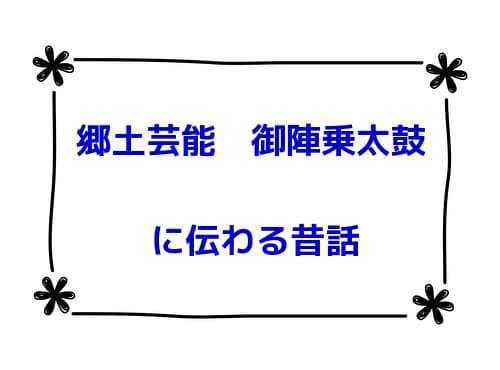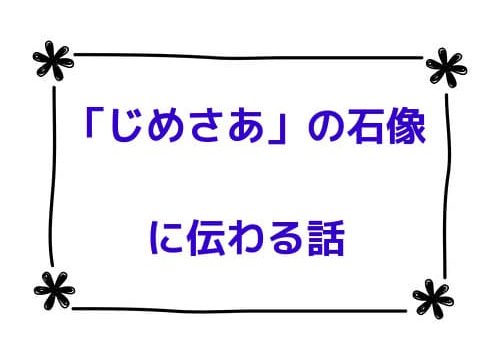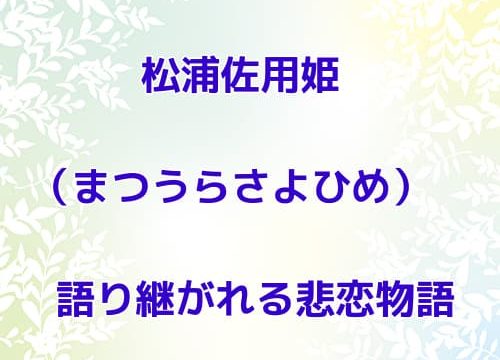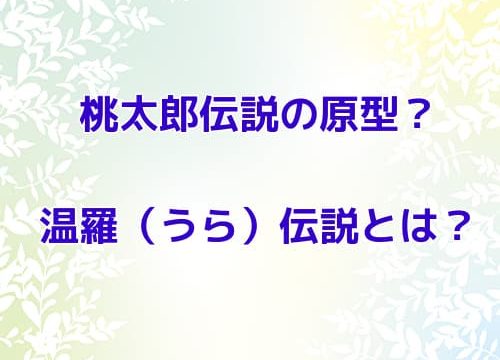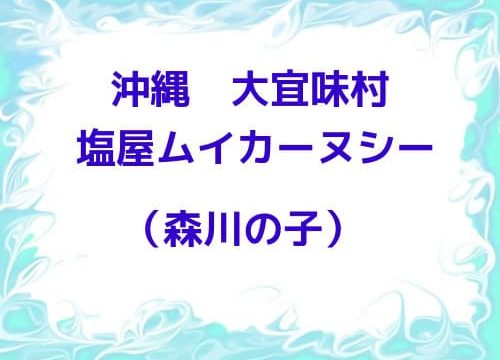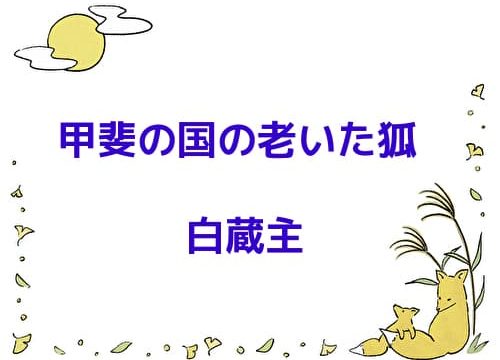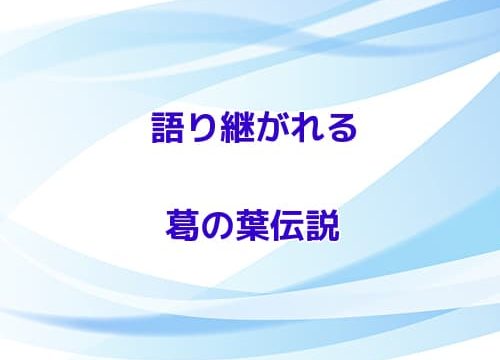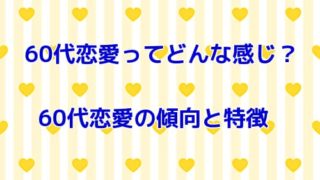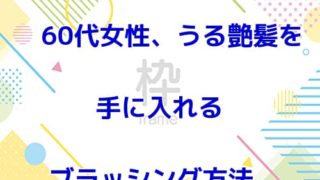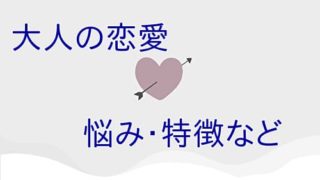動画を観るとわかりますが、輪島市名舟の御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)は郷土芸能の中でも力強く豪快で、徐々に激しくなる太鼓の響きは日本海の荒波を乗り越える力を与えてくれるようです。
御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)には昔から伝えられているお話があります。
Contents
郷土芸能 御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)に伝わる昔話
海藻をつけた奇妙な仮面をつけて、仮面に応じて力強く踊りながら太鼓を打つ姿は、何事も乗り越える勇士であるでしょう。
天正4年(1576)上杉謙信(うえすぎけんしん)は能登を攻撃しました。
昔話 御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)
天正4年(1576)上杉謙信(うえすぎけんしん)が能登を攻撃し、翌年には名舟村まで攻撃しました。
謙信勢は各地を攻め落とし、豊かな海の幸に恵まれた村々は危機が迫り風前の灯火でした。
武器など持たない村人たちは鎌(かま)や鍬(くわ)などで闘うしかなかったのですが、謙信勢を攻撃する準備を進めました。
「山に逃げた方が良いのでは」
「いや、潔く降参しよう。村を荒らされなくてすむのでは」
そんな会話をしていると、古老の一人が自分たちで村を守り抜くべきだと主張しました。
「わしに良い考えがある。皆の衆、木の皮に目鼻をつけて面を作るのじゃ。頭に海藻をたくさんつけて髪にする。そのあとに陣太鼓を破れんばかりに打ち鳴らせ。敵のどぎもを抜いてやるのじゃ!」
村人たちは古老の言う通りにしました。
村人たちは夜に先手を取り、敵陣に攻め込みました。
天地も震えよと太鼓を打ち鳴らし、謙信勢に夜襲をかけました。面を被った正体不明の荒れ狂う怪物たち。
謙信勢も予期せぬ奇襲に大慌てで退散していきました。
村人たちが力を合わせ勝ち取った勝利であります。
それ以来、日頃から信仰していた奥津姫神社の大祭に、奇怪な面をつけた若者たちが、陣太鼓を鳴らして神輿の先導をつとめるようになりました。
Gojinjo Taiko – For Tourism Ishikawa, JAPAN様YouTube御陣乗太鼓
Gojinjo Taiko – For Tourism Ishikawa, JAPAN様より。
奥津比咩神社
 奥津比咩神社(2013年)
奥津比咩神社(2013年)Wikipediaより
名舟大祭 7月31日夜から8月1日
大昔からご先祖様が知恵と勇気を伝えてきました。
小さな街ですが、ずっと大祭に力を入れて取り組んできたそうです。
おわりに
太鼓は最初はゆっくり、徐々に早くなり、激しく打ちます。
夜に神輿の海上渡御に、怖い面を被り、海藻の髪を振り乱した若者たちが櫓(やぐら)の上で太鼓を打ち鳴らします。
ご先祖様たちが大変な時も必死で乗り越えようとしてきたと感じました。
ずっと伝えていくことができますように・・・。
(参考)Gojinjo Taiko – For Tourism Ishikawa様YouTube、御陣乗太鼓公式サイト、Wikipedia御陣乗太鼓、北陸 民話と伝説