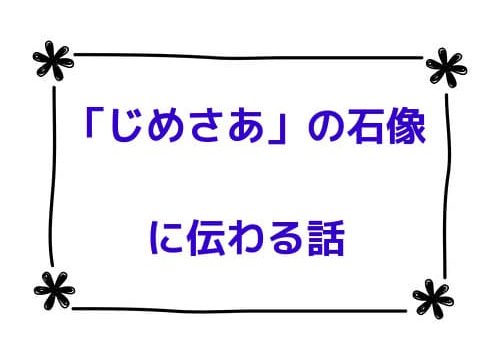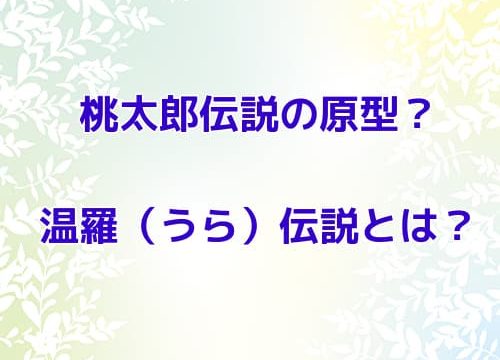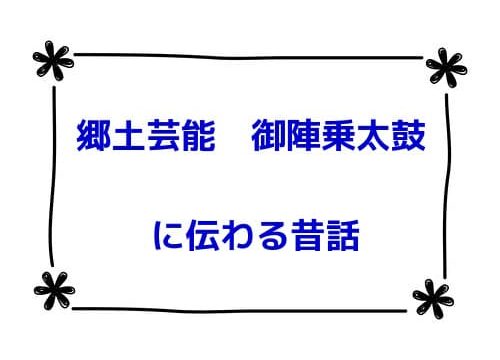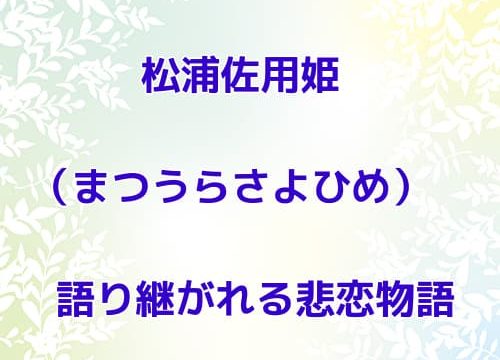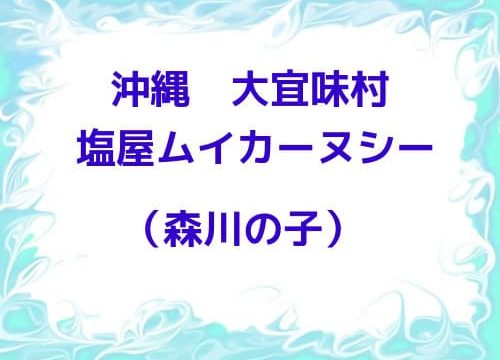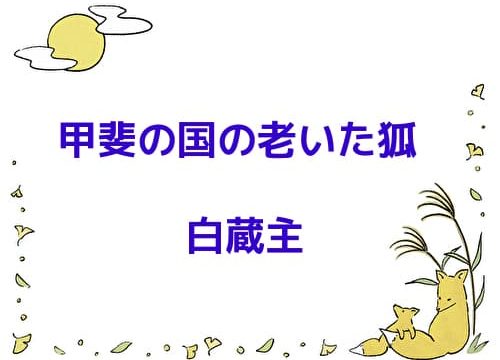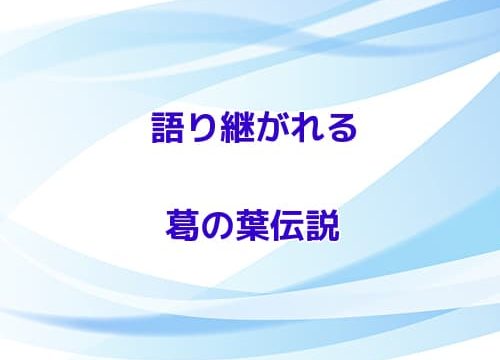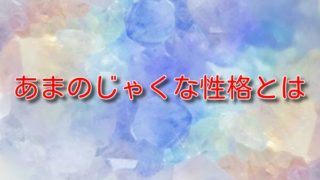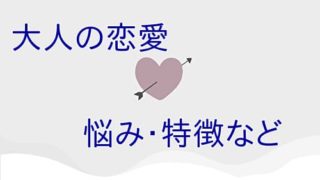ずっと大昔から変わらない「人のこころに存在する厄介なもの」この厄介なものがあるから、地上のあちらこちらに神々が存在するのだと昔話を読むと感じます。
何十年も何百年も生きてきた木に宿る神。山や海を守る神。火や水の神。
八百万の神(やおよろずのかみ)というのは、日本の多くの神様のことで、あなたの近くにも存在します。
たぶん、普段の生活の中では神様の存在を意識することは無いと思いますが、昔の人たちが大切にしてきた大きな岩や古木にも神様はいらっしゃいます。
人のこころに繋がる神が存在し、そこには豊かな世界があります。
確かなことは、小さな小さな神社でも守ってきたのは人間ですし、ご先祖様なのかもしれないということです。 心の中の厄介なものが現れると神を求める、すがるしかなかったりしますね。
ここでは有名な八百万の神(やおよろず)の中の女神のことを書いていきます。 前にもこんな記事を書いてます。
Contents
八百万(やおよろず)女の神様たちの恋愛、嫉妬、妬み、母としての強さ
昔話や伝説を読んでいると美しく強い女神たちが登場します。
エネルギーに満ちあふれ、自然の生命力の強さを感じることができます。
子を産み、エネルギーに満ち満ちている女性の神様をご紹介します。
木花咲耶姫神(このはなさくやひめのかみ)
 イラスト<abyss作>
イラスト<abyss作>桜の季節にこんな美しい女神がいることを思い出してください。
木の花が咲く・・・美しい女神様で、山の神「大山祇神(おおやまづみかみ)の娘で天孫二二ギ神「ににぎのみこと」と結婚して三人の子を産みました。
美しい木花咲耶姫神(このはなさくやひめのかみ)には多くの伝説が残されています。
木花咲耶姫神(このはなさくやひめのかみ)には磐長姫神(いわながひめのかみ)という姉がいます。
日本書紀では「石長比売(いわながひめ)」と書かれているので、山の岩の神ということです。
花はあっという間に散ってしまいますが、岩はずっとそこにあったりしますね。
長生きをするということで、良い組み合わせなのでしょう。
姉のいわながひめは妹のこのはなさくやひめとは違い、醜い容姿の娘でした。
ににぎのみことは美しい妹に惚れて父親のおおやまづみかみに結婚を申し込みました。
おおやまづみかみは姉妹をににぎのみことに送りました。
ににぎのみことは美しい妹のこのはなさくやひめだけを置いて、醜い姉のいわながひめは返してしまいました。
おおやまづみかみは「妹は木の花のようにはかない命。だから岩のように長い命の姉と二人を送ったのに、ににぎのみことの命もはかないものとなるでしょう」と言いました。
ににぎのみことの命は短いものとなりました。 姉のいわながひめは「私を妻に選んでいたならば生まれてくる子供は岩のように長い寿命をもったでしょう」と語ったのだとか。
人間の寿命が短くなったのは、ににぎのみことが木の花のように、はかなくて美しい木花咲耶姫神(このはなさくやひめ)を選んで結婚をしたからと言われています。
神様は平等に良いところを与えてくれるのですね。
※富士山本宮浅間神社・・静岡県富士宮市
※浅間神社・・ 山梨県東八代郡一宮町 その他約1300の浅間神社
※皇大神宮所管社 子安神社・・ 三重県伊勢市 など
天照大神(あまてらすおおみかみ)日本の総氏神
天照大神(あまてらすおおみかみ)は八百万の神のなかでも有名な女神で、伊勢神宮に行くのでしたら理解しておきたいですね。
天照大神(あまてらすおおみかみ)は天に照る神様ということで、天皇の祖神として伊勢神宮に祀られています。
「お伊勢様」と言われていますよね。 太陽神である天照大神(あまてらすおおみかみ)は地球上の生物が生きていく上で必要な太陽のエネルギーなのです。
子供の頃に読んだ本でずっと忘れることのできない話に、「天岩戸隠れ」というのがあります。
あまてらすおおみかみと弟のスサノオの2神が深く関わる天岩戸神話は、皇位継承の証である三種の神器が誕生する物語です。
あまてらすおおみかみのもとに居座っていたスサノオは田を壊したり、馬の皮を剥いだり、神殿に汚物をまき散らすなど乱暴なことを繰り返していました。
弟のスサノオ尊の暴力に耐えられなくなったあまてらすおおみかみは洞窟に隠れてしまい、戸をぴたりと閉めてしまいます。
世の中は真っ暗になってしまいました。 国中に災いが起きてしまいます。
「さあ、どうしたら良いものか」 そこで神々は鏡、その他のお供えものを用意して、あめのうずめがみがセクシーな踊り(ストリップ)を踊り、それを見ていた神々が大笑いをします。
興味を持ったあまてらすおおみかみは少し戸を開けてのぞきました。
そこを※(下記「参考」参照)天手力男神(あめのたじからおがみ)(最強の腕力を持っている)が戸を開けてしまいます。 世の中は明るくなりました。
この物語は日食と関係があるという説もあります。
古代の人々が太陽が隠れることを恐れていたと思えますね。
穀物の収穫を失う恐れに繋がると言われています。
あまてらすおおみかみは実は男神という説もあるとのこと。
実に勇ましい姿を見せるときがあり、弓矢をフル装備し、勇ましく戦う姿は男神そのもの。
途方もないパワーの持ち主であったとされています。
男性的なパワーを持っていたからと言われています。 皇祖神として崇拝されるようになったのは、このパワーへの強い信仰があったからということです。
※天手力男神(あめのたじからおがみ) 石屋戸の傍らに隠れて立っていて、あまてらすおおみかみの手を取って石屋から引き出しました。
長野県の戸隠神社は天手力男神(あめのたじからおがみ)が祭神となっています。
天手力男神(あめのたじからおがみ)が天石屋の戸を放り投げたときに、信濃国戸隠山に落ちたという伝説に由来しています。
※伊勢神宮・・ 三重県伊勢市
宮比神(みやびのかみ)(天鈿女(あめのうずめ)の別名)
 イラスト<abyss作>
イラスト<abyss作>
天鈿女命(あめのうずめ)の方が知られているのかもしれませんが、サルダヒコ神の妻とも言われています。
日本の芸能の始祖とされる神です。
天岩戸に隠れた天照大神(あまてらすおおみかみ)の関心を引くため踊りを披露しました。
上記ではストリップと書きましたが、盛り上がってくると胸をはだけ、衣を下げて舞い踊ったということです。(日本書紀より)
芸能の神とされていますので、現代でも芸人や俳優からも信仰されているそうです。
※芸能神社・・ 京都市右京区嵯峨朝日町 EXILE など多くの芸能人の方がお参りしています。
※椿岸神社・・ 三重県鈴鹿市山本町1871 など
神功皇后(じんぐうこうごう)
神の子を産む聖母として代表的な存在の神功皇后(じんぐうこうごう)は、母子神信仰として息子の応神天皇と一緒に神として祀られています。
母子神信仰は、霊的能力の高い女性が処女で受胎して神の子を産むという信仰です。
<鎮懐石伝承> 新羅遠征中におなかの子が生まれそうになったため、皇后は卵形の美しい石を2つ腰に付けて呪いとしました。
出産を遅らせようと祈ったので、築紫国で無事に出産をすることができたということです。
<鮎釣りの物語> 新羅遠征前の話となります。神功皇后は縫い針を曲げて米粒をつけたものを川にたらし「もしも遠征が成功するのなら、鮎よ、この針を飲みなさい」と言ったそうです。
するとたちどころに鮎が釣れて、皇后は大変喜び、「めずらの国」と名付けました。 これが「松浦(まつら)」の語源となったということです。
<肥前国風土記(ひぜんのくにふうどき)>
※香椎宮(かしいぐう)・・ 福岡県福岡市東区香椎4ー16ー1
※住吉大社・・ 大阪府大阪市住吉区住吉二丁目9番89号
※城南宮・・ 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町7 など
豊玉姫命(とよたまひめのみこと)
 イラスト<abyss作>
イラスト<abyss作>豊玉姫命(とよたまひめのみこと)は海の神様の娘さん。
姿かたちの見目麗しい(美しい)女性です。
妹が玉依姫命(たまよりひめのこと)神霊が依り憑く(よりつく)という意味で、神が依りつく巫女や乙女のことです。子供を産むということに結びつきます。
女性が子供を産むということは、凄いエネルギーであり、大切なことです。そこに神としてイメージされたのでしょう。(と思います。)
神話では豊玉姫命(とよたまひめのみこと)は海神の宮にやってきた山幸彦(ホオリ命)と結婚します。
子供は「うがやふきあえずのみこと」で神武天皇の父です。
この結婚で豊玉姫命(とよたまひめのみこと)は海の神の霊力と山の神の霊力をなかだちしたということになります。 富、権力、子孫繁栄の聖母神様です。
浦島太郎の昔話、龍宮城の乙姫様が豊玉姫命(とよたまひめのみこと)と言われているとのことです。
※山中諏訪神社・・ 山梨県南都留郡山中湖村山中御所
※高忍日賣神社(たかおしひめじんじゃ)・・ 愛媛県伊予郡松前町徳丸
※豊玉姫神社→・・ 鹿児島県南九州市知覧町郡
※鹿児島神宮・・ 鹿児島県霧島市隼人町 など
倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)
神話の中で三輪山の主である大物主神(おおものぬしのかみ)と神婚する女性として有名。
古墳の規模から相当に大きな力を持っていたと推測される。
卑弥呼のような巫女的な女王ではなかったか。
霊能力に優れ、崇神天皇の支配力を支えるような存在。
※田村神社・・ 香川県高松市一宮町
※𠮷備津神社・・岡山県岡山市北区吉備津 など
菊理姫神(くくりひめがみ)
地方の神様の菊理姫神(くくりひめがみ)は神話ではあまり活躍をされていませんが、大きなパワーを発揮されています。
加賀(石川県)の霊峰白山をご神体とする白山比咩神社の祭神。
「いのちの親神」と崇敬されてきた女神。 「白山さん」として親しまれています。
死者の霊を呼び出すイタコの先祖のような神。
農業・出産・育児の守護神。神徳、五穀豊穣・牛馬安産・縁結び・安産・生業繁栄・家内安全・交通安全・入試合格など。
※白山比咩神社・・ 石川県白山市三宮町
※白山神社・・新潟県新潟市中央区一番堀通町
※白山神社・・ 高知県土佐清水市足摺岬 など
そもそも「神様」って!?
日本の神様は物体でも生物にも宿ると言われてきました。
人に幸せを与えてくれると考えられてきましたが、災いももたらすと信じられていました。
生きていく上で人は普遍的なルールを破ってしまったり、タブーを犯したりすると災いが起きるというものです。
何気なく使っている「タブー」という言葉ですが、
超自然的な危険な力をもつ事物に対して、社会的に厳禁されている特定の行為をいう。世界宗教用語大事典より
神様は災いももたらすのです。
だからお供え物をしたり、お祈りをしたり、古代から神様を祀ってきました。
近所の小さな神社でも行ったときには、心を素直に持って丁重にお祈りしましょう。
昔から丁重に祀ると願い事を叶えてくれると日本人は信じてきました。
ずっと大昔から変わらない日本人の心を大切にしたいですね。
日本には多くの神様、八百万の神が存在すると言われてきました。
地域の風土記などを読むと、大きな岩や大きな古木が神とされ祀られています。
古木も大きな岩も、山や海などもご先祖様が大切にされてきたのだと気付くと、見慣れた風景も人と共存してきたのだと改めて感じることができます。
そのような気持ち、ずっと大切にしていきたいです。