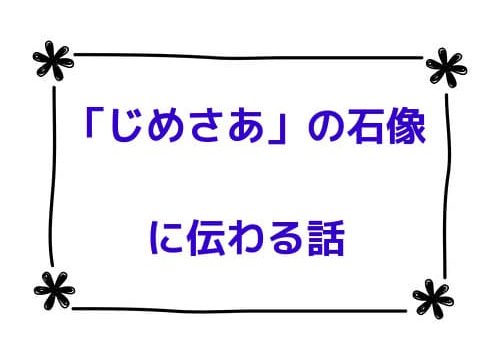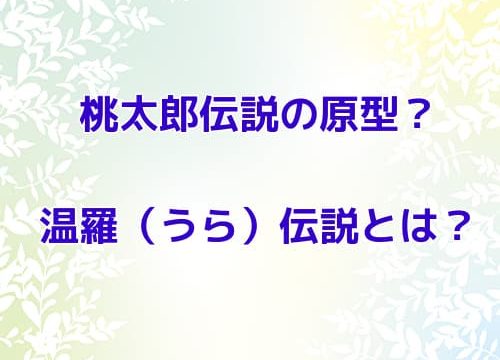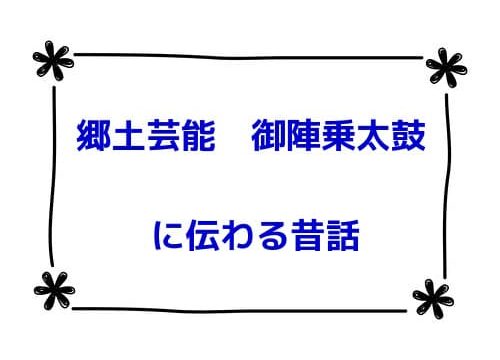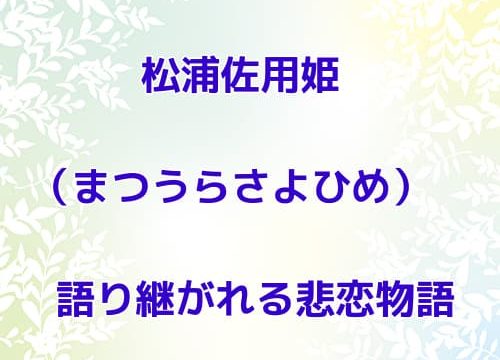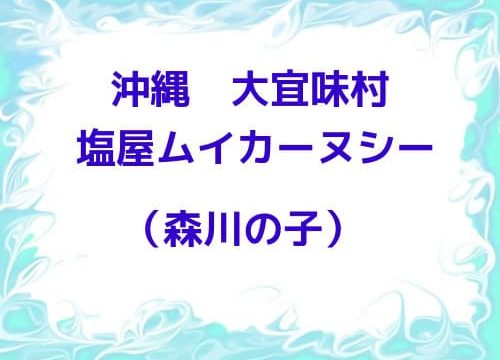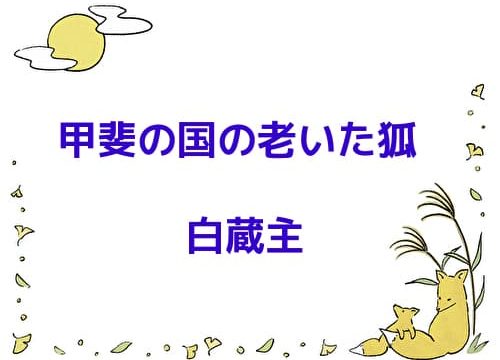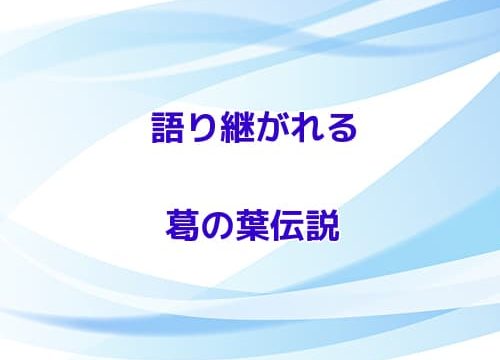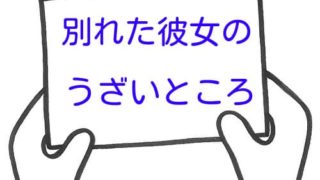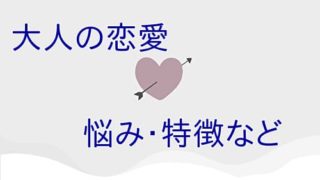昔々から暮らしの中で伝えられてきた伝説や民話を追ってのんびりと旅をする・・・特別な場所や人々に親しまれ、語られてきたその場所に行くと、伝説や民話とともに何かを語りかけてくれます。
有名な観光地でなくても、感動する景色がなくても感じることができる満足感。
昔話、伝説から東北地方の「哀しい女の物語」をご紹介します.
Contents
昔話、伝説から東北地方の「哀しい女の物語」をご紹介します
福島県福島市山口には愛する人の姿が映し出された「もちずり石」があります。恋する女性の切ない気持ちは今と変わらない女心。
杉の精とひととき人目を忍んで会っていたという話、村のためだと犠牲になった美しい娘の話など、東北地方の哀しい女の物語をご紹介します。
福島県福島市山口 文知摺石(もぢずりいし)
福島県福島市山口 文知摺観音(もぢずりかんのん)には「もちずり石」があります。
ここには、平安時代の初期の悲しい恋の物語が残されていました。
短く激しく燃えた恋が裂かれたとき、女はひたすら愛しい男の姿を求め、文知摺石(もぢずりいし)を麦草で磨き続けたという。
貞観年間(859年~877年)の話です。陸奥国按察使(みちのくのあぜち)として赴任してきた中納言 源融(みなもとのとおる)は、諸国探勝の一日に信夫郡山口を訪れました。
そこの長者に招かれもてなされ、長者の娘の虎女(とらじょ)に魅せられ親しい関係となってしまいました。
若い貴公子と美しい虎女は相思相愛となったのですが、叶わぬ恋とは知りながら、激しい恋の炎を消すことはできません。
虎女の心のわだかまりは現実に。都から戻るようにと源融(みなもとのとおる)の元に使いが来ました。
再会を約束して源融(みなもとのとおる)は後ろ髪を引かれる思いで都へ上って行きました。
残された虎女は源融(みなもとのとおる)に会いたい一心で観世音菩薩に百日詣りの願をかけました。
しかし九十九日が経っても観音の霊験は現われず、百日詣りの最後の日、失望のために重い足を引きずるように観音堂の前に立った虎女がふと近くの大石に目をやると、一時も忘れたことのない源融(みなもとのとおる)の姿が浮かんで見えました。
虎女が走り寄るとその姿は消えてしまいました。
観音堂詣りにすべての力を使った虎女はみるみると体が弱り、寝込んでしまった。
都の源融(みなもとのとおる)から便りが来ました。
「みちのくの忍ぶもぢずり誰ゆえに 乱れそめにし我ならなくに」
この便りを読んで虎女は安心して、数日後、短く哀しい生涯を閉じました。
これ以後、虎女が愛する人を見た大石を文知摺石(もちずり石)または鏡石と呼び、この石を麦の穂や草の葉でこすると恋しい人の面影が現われると言われるようになりました。
(参考・民話と伝説 東北)
福島県福島市笹木野 王老杉物語
昔々、信夫郡笹木野(福島県福島市笹木野)に「おろす」という美しい娘がいました。
いつの頃からか一人の若者が人目を忍んでおろすのもとへ通うようになり、毎日のように会うようになっていました。
おろすは若者が夜しか姿を見せないことに不審を抱いていて、ある日のこと、糸をつけた小針を若者の袴の裾に刺して別れ、ひそかにその後を追ってみることにしました。
村一番の大杉の前で若者は姿を消してしまい、おろすは驚き大杉に近づいてみると、小針が根元に刺さっていました。
「大杉の精だったのか。名前も言わず、夜しか姿を見せない理由はこれでわかった」おろすはこれまでの出来事を村人に話しました。
放って置くとまた村の娘に取り憑くかもしれない。相談の上、この大杉を切り倒すことにしました。
ところが大きな大きな杉は一日では切り倒せず、切りかけのままその日は村人は帰ってしまいました。
次の日に村人が行ってみると、切ったはずの切り口はふさがり、こんなことが十日も続くと村人も恐れていました。
そこに現われたよもぎの精は、「切り口から出る木くずを燃やしてしまえば良い」と言い、その通りにすると大杉を倒すことができたのです。
よもぎはなぜそのようなことを言ったのかというと、前に大杉に「おまえは草だ」と言われ恨んでいたから。
切り倒した杉で福島の城に橋をかけようと川を流して運んでいる途中によもぎがまた現われて、杉の悪口を言いました。
怒った杉は逆戻りをして流れようとしなかった。この地を「杉上がり」と呼んでいます。
そこでおろすに頼んで杉をなだめてもらい、ようやく福島まで運ぶことができました。
やがて橋は完成。しかし、この橋を渡ろうとすると、「おろす、おろす」とささやく声が夜な夜なし、だれもが気味悪がって渡ることができなくなったといいます。
再び呼び出されたおろすは、優しい手で橋を愛撫するとささやきはしなくなった。この橋を「ささやき橋」と言うようになったのだとか。
村の人々は結ばれなかったおろすと杉の精を結びつけ、この杉を「王老杉(おろす)」と呼んでいるのです。
(参考・民話と伝説 東北)
宮城県登米郡中田町(現・登米市) お鶴明神
鶴のように美しい少女の話です。
穀倉地帯を潤してくれる北上川は沿岸に住む人たちにとっては豊穣(ほうじょう)を約束してくれる大切な川です。
しかし一度大雨が降ると、暴れ狂い人々を大いに苦しめました。
当時、北上川はどんな壊れにくい堤防を築いても大雨が降ると容赦なく壊してしまいました。
ある年のこと、大雨は止むことなく連日降り続き、水かさを増すばかりでした。里人は早く止んでくれないかとため息ばかり。
その頃、登米の城主は伊達兵部(だてひょうぶ)という人で、彼は里人を水禍から守ろうとしていました。
年老いた家臣が「これは水神の祟りに違いありません。昔から水神を鎮めるためには美しい娘を人柱にすれば良いと言われています」
兵部は年老いた家臣の言葉に従うことにして、村一番の美しい娘のお鶴を選びました。
お鶴は悲しみ、毎日涙に暮れていましたが、とうとう人柱にされる日がやってきました。
お鶴は長い髪を背中で一束にまとめ、白い着物に身を包み、震えながら土手の上に立っていました。
その純真な姿は一羽の鶴のようで、村人たちはお鶴を見守っていました。お鶴は人柱となり、長い若狭土手が築かれました。
それからというもの北上川がどんなに暴れても提は崩れることなく、村は平和となったのでした。これはお鶴のおかげだと人々は感謝してお鶴を埋めたところに社を建てお鶴明神としました。
社の近くにはお鶴の涙池もあり、水神のいけにえとなったお鶴をしのぶ村人たちの信仰を伝えています。
(参考・民話と伝説 東北)
※お鶴の涙池は明治時代に理没されましたが、その後復元されています。