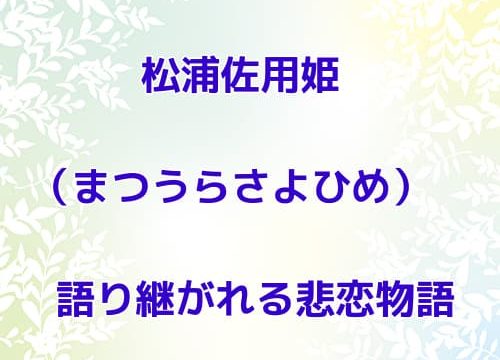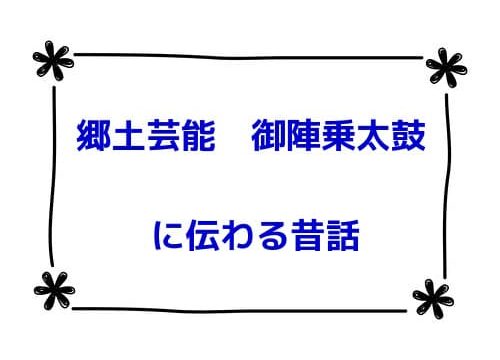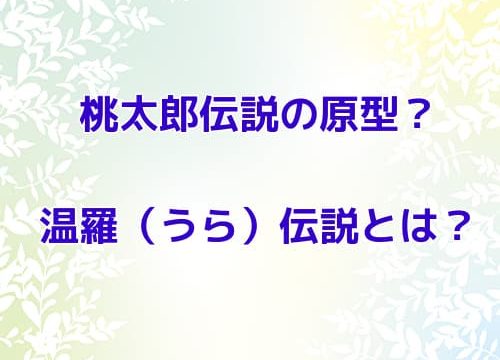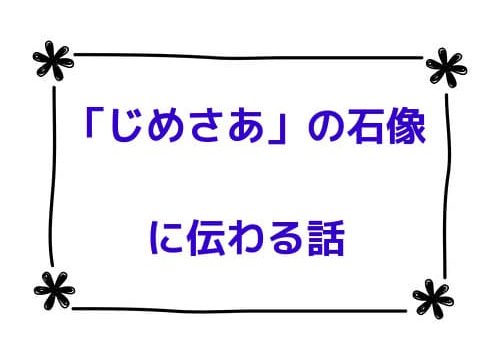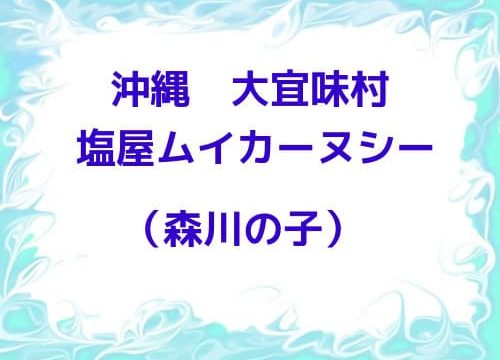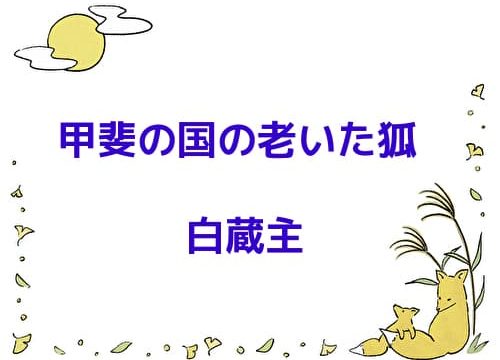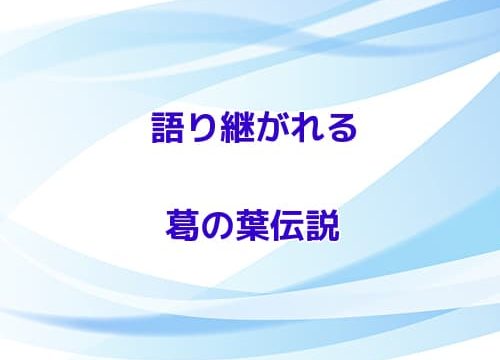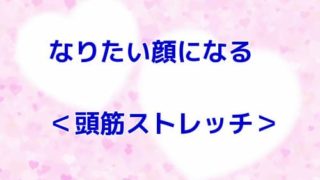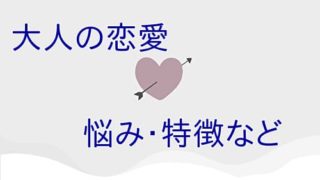伊豆の天城山は伊豆半島の中央部の東西に広がる山々の総称で、万二郎(ばんじろう)万三郎(ばんさぶろう)、遠笠山(とおがさやま)などの山々で成り立っています。
ハイキングで行ける所もありますが、本格的な山登りをする方達もいらっしゃいます。
紅葉も綺麗ですし、ドライブもおススメです。
古い本で見つけたのですが、「天城山と富士山と怪物」の伝説で天城山には「鬼」が棲んでいて悪さをしたと書かれていました。
昭和の初め頃に発行された本で、書き始めが「昔、昔・・」で始まっているので相当昔の話なのでしょうね。
「天城」の出典ですが、説はいろいろあるようですが、✅昔、天城山中に自生している甘木(あまぎ)の葉から甘茶を作り、朝廷に奉ったので天城山の名ができたと言われているそうです。
甘木の葉はヤマアジサイよりも葉が細くて甘味が多いとのこと。
この葉をもみ、天日で乾かして湯を注いで飲んだと書かれています。(昭和の初め頃の話です)
低木では他にクロモジなども自生しています。
他にも天城は✅「天限り」の意であるとも言われているそうです。字のままの解釈で良いということです。
もう一つ、天城は✅「天降り」であるという説もありました。天城は雨が多いです。
南伊豆の暖かい水蒸気が天城の峯の冷気のあたって雨となると昭和の初めに発行された本には書かれていますが、それより前には天城に多くの雨が降るということは、不可解な現象だと捉えられていました。
さらに一つ、✅天城とは「天子在城」の意であるという説もありました。
君主が存在したと思いたかった・・・?
天城に棲む「天の邪鬼」
昔、昔の話です。
天城の山には「天の邪鬼」という怪物が棲んでいました。
天の邪鬼は恐ろしい力がありました。この怪物が峯の山々をかけまわると烈風のような音が響き渡りました。
ある日、天の邪鬼は山の上に立って遠く北方の空を眺めると、そこに高い山が見えました。
空高くそびえる富士山です。
「あの山は俺の山よりも高いぞ。生意気な山だ」
天の邪鬼は、山の上を踏み鳴らすと、山や谷が鳴り響き、峠はうなり続けました。
天の邪鬼は「富士山を切り倒してやる」とつぶやきました。
早速その日の夜に天の邪鬼は駿河の富士へ出かけていき、頂上の土を掘り取っては伊豆の海へ棄てたのです。
夜が明けると天城へ帰り、日が暮れるとまた駿河の富士へ出かけていき、この労働を続けたのですが、なかなか小さくならない富士山。
天の邪鬼は疲れてしまい、この作業を中止したのです。
天の邪鬼の切り崩したあとは、今も富士山に残っています。
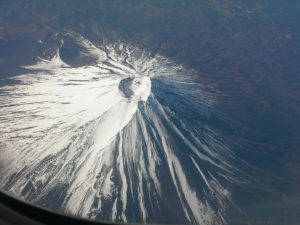 富士山(Wikipediaより)
富士山(Wikipediaより)伊豆の大島は、天の邪鬼が棄てた土でできた島で、箱根の二子山は邪鬼が運ぶ途中に落ちた土でできたと言われています。
(参考文献・伊豆伝説集)
天の邪鬼の話で、付け加えられていることがあったので追記します。
天の邪鬼はほうそう神が大嫌いで、伊豆にほうそうが流行ってくると、怒ってほうそう神に土のだんごをぶつけて追い払ってくれたといいます。
「ほうそう」というのは天然痘のことで、怖い、怖い伝染病だったのです。
だんごの真ん中に赤い点をつけたものを「山の神(天の邪鬼)」に供えると、天の邪鬼がほうそう神を追っ払ってくれるというので、このおだんごを「ほうそうだんご」と言います。
ほうそうよけのおまじないでほうそうだんごを供える風習があったとのこと。
また天の邪鬼は子供が大好きで、子供が病気で寝ていると、枕もとにやって来て、子供の面倒を見てくれたとも伝えられています。
でも子供をほったらかしにしていると、天の邪鬼が連れていってしまうとも言われていたようです。
子供が泣き止まないと「泣いていると鬼がくるよ」とか言っていたのかもしれませんね。
天城の天狗
昔、天城山には万治郎天狗と万三郎天狗という仲の良い兄弟の天狗が棲んでいました。
八丁池で水遊びをしたり、すもうをとったりしていつも仲良し。今でも兄弟がすもうをとっていた所が天狗平とか天狗の土俵場と呼ばれています。
ある日、すもうに疲れて前方に見える富士山を眺めていると、「あれをぶっかいてやるか」ということになり、夜になるのを待ち、大きな鍬とモッコをかついで富士山に向かいました。
兄弟の天狗は富士山の頭を欠いてはモッコに入れて、天城山まで運びました。
一晩中それを繰り返していた天狗たちは朝になり富士山を見て驚きました。
醜くしようと思ったのに、富士山は「何も変わっていなかった」のです。それどころか美しくなったような気がします。
「骨折り損のくたびれもうけだ」
兄弟の天狗はばかばかしくなってかついでいたモッコを放り出してしまいました。
この途中で放りだされたモッコの土でできたのが箱根の双子山だといいます。
((参考文献・伊東の民話と伝説)
富士山に伝わる昔話などを集めてみました。
古事記や神話に富士山に関連する伝説が残されています。
他の地域にも残されている伝説などもまとめてみました。
日本を象徴する富士山の神霊、木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)の話と富士山に関係する民話・伝説を紹介しています。
大昔から多くの人に愛されてきた富士山は強い霊力があるとされ、信仰の対象とされてきました。
まとめ
富士山が美しく高くそびえるので、近くの山々が嫉妬して、おもしろい伝説がたくさん残っています。
「大きな大きな鬼は、怪力で、天城山をかけまわり、山も谷も振動させていた」このようなことが書かれている伝説もあり、この大きな鬼がかけまわると地震が起きていたのかもしれませんね。
そして感じたことは昔から郷土を愛する人たちによって、「郷土愛」が語り継がれているということです。
伝説によると天城山には怪物も棲んでいたようですが、天城山には、スギ、マツ、モミ、ケヤキ、ツガ、ヒノキ、カヤが天城七木と称され、鎌倉時代から良材とされました。
これらの良材で舟を作ったと伝えられています。
また江戸時代から薬草の産地として知られてきたそうです。
だから天城邪鬼は富士山を掘ることなどしなくても、自慢できることはあったと思うのですが。。。(笑)